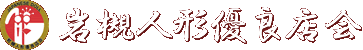こちらでは、雛人形の飾り方・しまい方。着付け、髪型などの細部。大きさ、その他の内裏たち囃子の名称・役割、そして周りを彩る大事なお道具について。また、あまり知られない雛人形作家の製作過程について触れていきます。
特別な決まりごとはありませんが、日本人は昔から四季折々の行事を楽しむことを好んでいましたので、早めに飾ることをおすすめします。 初節句の場合は通常の場合より2~3週間早く、一ヶ月少々飾る方が多いようです。一般的に雛人形は2月の節分の前後が多いようです。 大安・友引に飾り付けをするとよいと言われています。遅くともお節句の1週間前には飾るようにしたほうが良いでしょう。 昔から「一夜飾り」といって前日に飾ることは嫌う習わしのようです。
飾り方
人形の向きはどちらでも飾りやすい場所がベストですが直射日光の当たる場所は避けましょう。
まず飾る前にお部屋の掃除をしておきましょう。
しおり等で手順を確認します。飾る順に箱から出すとよいでしょう。
しまう時のためにどの箱に何が入っていたかをメモなどにしておくとよいでしょう。
(段飾りの場合)
- 緋毛氈(ひもうせん)を掛けます。先に左右を合わせて最下段から順に歩上ピンで止めます。
- お雛さまを用意します。飾るときには薄手の手袋を着用して、お雛さまなどの顔や手、金具などに直接触れないように注意しましょう。
特にお顔は触らないように。 - お雛さまを最上段から順番にまた奥から並べていきます。手前を先に飾ると奥のものを飾る時に落としたりしますので、気をつけましょう。
- 雛道具を飾ります。特にこれといった決まりはないので、全体のバランスを考えて飾ります。同封のしおりを参考にするとよいでしょう。
雛人形の飾り方については、特別厳格な決まりがあるわけではなく、その時代、地方によって、かなり違いが見られます。
しまい方
「早く片付けないとお嫁にいくのが遅くなる…」というのは、昭和初期につくられた迷信です。片付けは、季節の節目という本来の意味からなるべく早め、遅くとも三月中旬までに済ませておきましょう。啓蟄(けいちつ)、3月6日頃を目安としてください。啓蟄とは二十四節気の一つで、冬の間地中にいた虫が這い出てくる頃です。飾る時と同様、薄手の手袋を着用し、お顔や手、金具などに直接触れないようにするのがよいでしょう。お天気の良い乾燥した日を選び、ホコリをよく払い、柔らかい紙でくるんで人形専用の防虫剤を入れて収納しましょう。保存場所は湿気が少なく、また乾燥もしすぎない押入上段や天袋などが適しています。秋に一度、陰干しすれば万全です。
付属の持ち道具ははずします。
本仕立て着付け
並着せ
優雅さをあらわす髪型
髪は女の命ともよく言われますが、それは雛人形とて同じことです。髪型にも意味があり、例えば以下の「垂らし髪」「おすべらかし」などがあります。より優雅さをあらわし、殿の横に座る雛は、一層美しいことでしょう。
サイズの表示は専門用語が使用されています。
柳(やなぎ)、芥子(けし)、三五(さんご)、十番(じゅうばん)、九番(くばん)、八番(はちばん)、七番(ななばん)と順に大きくなっています。 最近はわかりやすいように㎝で表示しているお店もありますので、わからないときは遠慮せずに尋ねてみるとよいでしょう。 また、お店で見た時と家で飾った時は大きさに違いを感じることもあるようです。できれば出かける前に飾るところの寸法を測っていくことをおすすめします。
雛人形は一般的には母方のご実家から贈られることが多いようですが、 父方から贈られる場合や、ご両家からのお祝い、ご夫婦自身でご購入など様々です。 父方のご実家もなにか形に表したいという方も多いので、「初節句お祝い」を若夫婦に差しあげたり、市松人形を贈るなどの場合が多く見受けられます。 販売店等にもよりますが、お届け日はご都合の良い日を選べるでしょう。ただし、1-2月の吉日といわれる日はお届けも多いのでご希望日が叶わないこともあるかもしれません。 また、 季節商品ですので、完売すると追加製作が困難となります。 これはと思うものがあったら、予約をしておいたほうが安心です。
それぞれの名称など
几帳面の語源となったもので、二本のT字型の柱に薄絹を下げたのれんの様なものを言います。この几帳の柱の角を落として面取りをするという作業は とても正確な技術が必要であったことから、「几帳面」というようになったのだそうです。几帳は、移動可能な隔ての道具です。内部を小間に仕切る為に使ったり、どこにでも置くことができ、大間を小さい空間に間仕切るのに重宝だっのです。
最近の雛人形は、屏風か几帳を背に飾ることが主流のようです。
現在は木やプラスチック製のものがほとんどです。
雛人形のお道具としては、二段重ねの紅白の丸いお餅や和菓子などを載せています。
菱餅(ひしもち)は和菓子の一種で桃の節句に雛人形とともに飾ることでも知られています。
初めは蓬(よもぎ)に菱の実を組み合わせた緑と白の2色だったものが現在のように山梔子(さんしし。クチナシの実)を加え3色となっていきました。
それぞれの色には諸説ありますが、大地の緑・雪の白・桃の花の桃色というように自然の色にたとえた由来、緑が健康や長寿、白が清浄、ピンク(紅)が魔除けを表しているという由来があります。
こちらも婚礼道具の一つとして数えられていたことから、雛人形のお道具として飾るようになったようです。
お雛様は京都御所をモデルにしたものです。京都御所のお庭に植えてあります。
近年では愛子さまのお誕生の際に、天皇陛下から贈られて、脚光を浴びています。
- 人形の頭(かしら)の原型を造る釜に、目を入れて石膏を流し込んで固めます。
- 釜から取り出し人形の顔の形ができあがります。
- 細い筆で、入念に髪の毛の生え際に墨を入れていきます。
- 眉、まつ毛を丁寧に描きます。
- 口紅を入れ小さな口もとに舌や歯をつけます。
- 塗り重ねた所から彫刻刀などを使い目を切り出して、面相の完成です。
- 額の溝に毛を平均に植え付けていきます(植毛)
- 毛ブラシで整えながら結い上げていきます。(結髪 けっぱつ)
- 最後にたまぐしを付け、お顔の完成です。
- 胴体を作ります。藁で作った胴に針金を通 し、藁を巻き腕や足を作ります。
- 縫製した袴をはかせます。
- 首元に袴を重ね合わせていきます。
- 中襦袢を着せます。
- 人形サイズに合わせ、着物を丁寧に縫製します。
- 着物を形良く着せ付けます。
- 上着になる唐衣(からころも)を仕立てます。
- 唐衣をバランスよく着せ付けていきます。
- 背中に裳袴をつけた十二単衣の優雅さを出します。
- 正面に裳袴の帯を取り付けます。
- 左右の腕を曲げ全体の形をとり胴体が完成します。
- 頭を首元に差し込みます。全体の形を整えると雛人形の完成です。